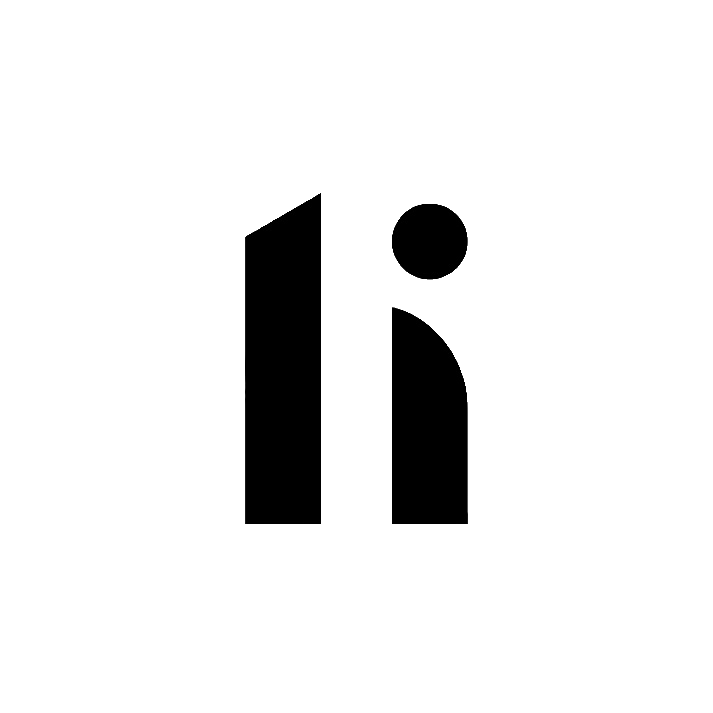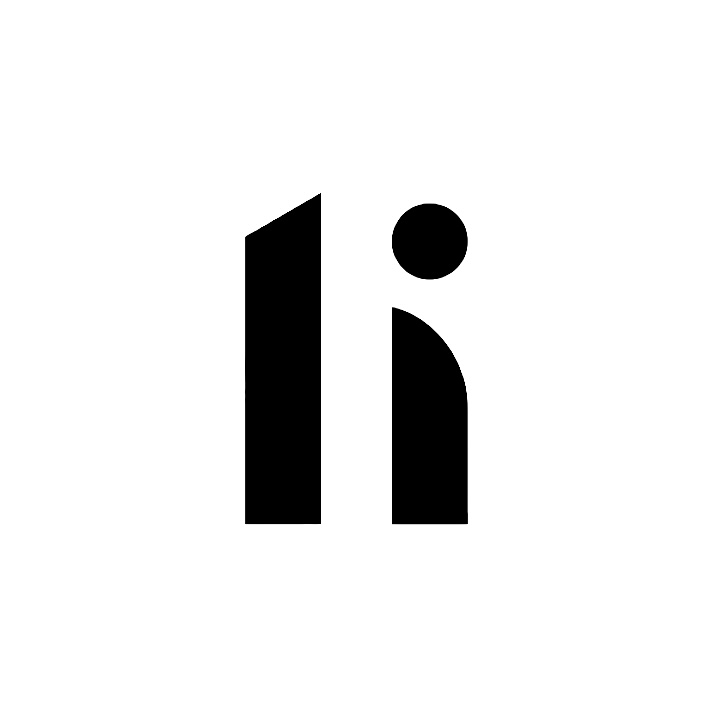十二月の朝は、ほかの月と同じ顔をしていながら、どこかで一枚だけ違う膜をまとっている。窓を透かして入ってくる光は、白いのに冷たさの芯だけ濃く、こちらの皮膚ではなく、思考の表面にじかに触れてくる。目を覚ましたとき、部屋の空気は昨夜の匂いをきれいに手放していて、新しい紙束を裂いたあとのような乾いた感じだけが残っていた。私はしばらく天井を見つめ、それから身体を起こし、ベッドの端に座って、足を床に下ろした。フローリングの冷たさが、今日の輪郭を、言葉より先に足裏から押しつけてくる。
手を伸ばすと、ベッドサイドに置かれた Jaeger-LeCoultre Reverso が、薄い朝の光を鈍く返した。指先でケースをつまみ上げると、簡潔な金属の重みが掌の中心に落ちる。その重みには、使われていない面の沈黙まで含まれていた。盤面の表裏を返す構造を持ちながら、時刻そのものは揺るがぬまま積み重ねられる。眠っている面が裏に伏せられたまま、薄い金属の奥で息をひそめているようで、その沈黙が、日常に隠れている別の層を意識の端に浮かべる。
革のストラップを手首に巻くと、金具が小さく音を立て、時刻だけがそこへ落ちる。針が示す刻みは、早朝の空気を裂くように進み続ける。金属の冷たさは、外気のそれではなく、今日という日付がもつ始まりの気配と呼応していた。
スマートフォンを手に取り、日付のところに指を滑らせる。十二月八日。その数字の並びを目に入れたとき、胸の奥に小さな軋みのようなものが生まれる。祝祭日でも記念日でもない。ただ、ある朝の一報を境に、すべての線が別の方向へ折れ曲がってしまった日ということを、この都市に生きる多くのひとは、意識していないか、意識しないことに慣れている。だが日付の数字だけは、何も語らぬまま、同じ位置に居座り続ける。始まりだけを告げておいて、そのあとに続いたものについて何ひとつ説明しない、冷たい標のようなものとして。
ニュースアプリには、あいまいな見出しがいくつか並んでいた。「あのとき、なにが起こっていたのか」「開戦日に考えるべきことは」。触れれば、当時の写真や口述がどこまでも流れてくるのだろうが、指先は自然にそのアイコンを避けて動き、為替のアプリを開く。数字の列は、私が眠っているあいだも律儀に動き続けていたらしく、円は静かに、高いほうへ伸びている。画面に赤い四角が増え、いくつかの銘柄名が鮮やかな色で点滅していた。
この数字の配列が、どれほどのひとの顔色と胃の調子を変えるか、だいたい見当がつく。誰かの声が高くなり、誰かの声が低くなり、誰かは上司の前で言い訳を探し、誰かは踏み台として席次をひとつ上げようとする。私はコーヒーを一口飲み、画面を閉じる。私にとって大事なのは、この数字を使ってどんな言葉を並べ、誰の心拍をどれほどの高さに保つか、ということにすぎない。
駅までの道を歩きながら、私は街の様子を横目で見ていた。通りの角には、多くの箱が乱雑に積まれ、出勤のひとたちが淡々と流れている。花束も、式典の椅子もない。スピーカから特別な音楽が流れることもない。今日が何の日か、わざわざ他人に告げる者はいない。むしろ、この沈黙そのものが、この日付にふさわしいのだろう。始まりに拍手は要らない。ただ、気づいた者だけが、自分の呼吸の速さがわずかに変わっていることを自覚すればそれで足りる。
会社のフロアに入ると、外の冷たい光は、蛍光灯の均一な白さにすぐ溶かされる。ガラスの先の空の色は、ここではあまり意味を持たない。重要なのは、モニタに並ぶ数字の配列と、そこにぶら下がっている人間の心理のほうだ。端末を立ち上げると、画面は予想どおり赤が多く、緑は点のように散らばっている。電話はいつもより早く鳴り始め、オフィスのざわめきがひとつ高い段に上がる。
私のスケジュールには、十時から面談がひとつ入っていた。ひらがなと漢字が混ざった控えめな名前。その文字列を目にすると、ガラス張りの会議室の光と、窓際の椅子と、膝上のスカートの布の落ち方が、頭のなかに同時に立ち上がるようになっている。
会議室に入ると、彼女はいつもの席に座っていた。淡いベージュのジャケットに、紺の膝丈スカート。ブラウスは白ではなく、ごく薄いクリーム色で、生地はわずかに透け感がある。胸元は上までボタンを留めているが、布の下に潜むものの気配を完全に消しきるほどの厚さはない。肩までのボブは、耳をほとんど隠して落ちていた。化粧は控えめで、唇の色も強くはない。全体として「地味」と評される範疇に、きちんと収まる姿だった。
それでも、彼女が椅子に座っているのを見ると、その座り方が目につく。背筋を無理に伸ばしているわけではなく、かといって緩ませてもいない。骨盤のどのあたりに重心を置けば疲れずに長く座っていられるか、身体で知っている座り方だ。膝は揃えられているが、膝を押しつけているような緊張はない。スカートの布は膝になめらかな波をつくり、皺を拒むように静かに落ちている。
離婚を話す彼女の声は、淡々としていた。慰謝料の額、元夫の仕事、実家の事情。どの要素も、すでに彼女のなかで何度か反芻された言葉として出てくる。怒りや嘆きは、少なくとも表層には現れない。そのかわり、言葉と言葉のあいだに少し長めの溝があり、その溝を覗き込めば、別の色の液体がゆっくりと溜まっているのが見えるようだった。
私は必要な数字だけを拾い上げ、紙にいくつかの選択肢を並べる。彼女はうつむき加減に紙を見つめ、指先で書類の端を押さえた。指は細く、爪は短く切り揃えられ、何の色も乗っていない。その素っ気なさが、かえって手のかたちの整いを際立たせていた。紙にかかる力が、ある行のところでわずかに強くなり、すぐに戻る。それだけで、その行が彼女にとってどういう重さを持つのか、だいたい察しがつく。
数回目の面談のとき、彼女は椅子から立ち上がろうとしてパンプスのかかとをテーブルの脚に引っかけた。身体がほんの少し傾き、バランスを取ろうとして伸ばした腕に引かれて、ブラウスの胸元の布がふっとずれる。その一瞬、上から二つ目のボタンと三つ目のあいだから、内側の布が細く姿をのぞかせた。
色は、夜のバーの隅で見る葡萄酒の底のような、黒に近いワインレッドだった。生地は薄いが密度が高く、表面に花弁のような小さなモチーフが連なっている。花びらの縁はごく細い糸で縫い留められていて、その糸が照明を受けて微かな光を返す。カップの上辺はまっすぐではなく、ゆるやかな波を描いて胸を縁取り、その波の低いところにだけ肌の色がわずかに滲んでいた。飾るための構造と支えるための構造が、ぎりぎりの線で折り合いをつけたようなデザインだった。
胸のふくらみそのものは、布にきちんと収められている。見えているのは、飾りのレースが重なるところだけだ。それでも、そのレースがどのようなかたちで胸を囲んでいるのか、どのくらいの高さから肌を包んでいるのか、想像してしまうには充分だった。肌と布の間にどれほどの空気が残されているのか、あるいはほとんど残されていないのか考えることは、私にとって仕事には係わらない計算でありながら、いささか集中を要した。
彼女はすぐに姿勢を戻して、ブラウスの裾を乱暴にならないほどの速さで整えた。頬がわずかに熱を帯びたかどうか、判らない。ただ、椅子に座り直したとき、膝を揃え、膝で両手を組んだ指がひと呼吸のあいだだけ強くかみ合い、すぐにほどけた。その短い圧力のなかに、「見られた」という事実と、「見せてしまった」という感覚と、それでも構わないという諦念にも似た静けさが、ごく薄く、薄く混じっているように見えた。
その布の現われ方は、たんなる「見せてしまった」という類のものではなかった。光と布と肌のあいだに生まれた、ほんの薄い隙間から漏れた影の層が、思いがけず深く沈んでいる。淡い照明がひと息ぶれるだけで、その影は花弁を幾重にも重ねた布の奥へ吸い込まれる。仄暗さにそっと指を乗せたときの温かさの名残だけが、指先におりたような錯覚さえ呼んだ。
その濃密な影は AGENT PROVOCATEUR の布が持つ独特の気配と通じていた。直に見えるものはほとんどないのに、その織り目だけが、静かに存在を主張している。光の下では語られない構造が布の奥に潜み、肌を縁どるレースの蔦のような模様が、見えていないところのかたちまでほのかに示唆していた。細い糸で編まれた模様が、光を細かく噛んで、ほんの瞬きほどのあいだに浮かんでは消える。
均一な光に満ちた職場のなかで、その布の影だけが別の時間の灯りに属して、胸元のわずかな揺れが、その時間へ通じる細い裂け目をつくっていた。
その日を境に、私は彼女の外殻を以前よりも注意深く見るようになった。彼女の外殻に触れるたび、その継ぎ目のどこかしらから、昼の光では拾いきれない気配が、わずかに漏れている。彼女自身、なにか大きく変えたわけではない。ジャケットもスカートも、色味は相変わらず控えめで、アクセサリらしいものも見当たらない。だが、彼女の身体を覆う布のどこかに、胸元で見たあの影の残響が、細い震えとなって潜んでいる気がした。
彼女が高い棚の書類へ手を伸ばして身体をわずかに傾けたとき、膝のうえに落ちていたスカートの布が、ごく静かにずれて、その滑った布のあいだから、薄い光がこぼれるようにして影が細く立ち上がった。その影は、蛍光灯の均一な明るさに照らされて、まるで部屋の光がそこだけくぐもり、どこか別のところへ紛れ込んでいるかのようだった。
わずかな膝の動きに呼応して、かすかに影を震わせる。膝を揃えようとする、その一瞬の隙間を縫うように、ワインレッドの色がわずかに沈んだ。黒の底へゆっくり沈む葡萄酒の滓のように、深い層が静かに覗き、その深さだけが光を拒む。AGENT PROVOCATEUR のレースは、その拒む力を布の奥で密かに抱えて、花弁の縁に潜む細い糸の密度が、影へ沈む速さを重くしていた。肌は平らで、影は滑るように動く。レースの凹凸が映らぬほど慎ましいのに、光に触れたところだけが薄い膜のように透き、確かな存在だけが淡く潜んでいた。飾りのための織りと、支えるための織りが、互いを侵し合いながら結び留められている。
彼女はすぐに膝を揃え、布を整えた。影は引き、スカートの波は消えて、整えたあとの静けさに、かすかな温度が残った。「見られた」という羞恥ではなく、「見せてしまった」ものを把握するための、一瞬の集中。その集中が、膝にのせる指先のかたちをわずかに固くして、ほどけるまでの一拍を長くする。戻ったあとの空気には、触れた影の温度はほとんど残らず、ただそれだけが、透明な記憶として場に薄く漂う。
それは前兆とは呼べないほど淡い。だが、見過ごせるほど薄くもない。見せようとしたのではない一片の布が、一瞬だけ現われて、その一瞬だけが、日常にひと筋の縦糸のように差し込む。影は、彼女の膝のわずかな揺れに滞り、またすぐに散っていく。
昼食を摂って、私は廊下から彼女の席のほうを何気なく眺めた。彼女はバッグを膝にのせ、中身を整理しているところだった。メモ帳やポーチの間から、小さな箱が滑り出し、膝で止まる。明るい照明のもとで、その箱は小さな飾り物のように見えた。表面はマットブラックで、中央に銀色の細い文字が浮かんでいる。箱の蓋はほんの少しだけずれていて、柔らかな紙に包まれた布が見えた。紙は薄く、ところどころにレースの影が透けている。彼女はすぐにそれを指先で押し戻し、箱ごとバッグの底へ沈めた。その動作は、慌てた様子とは違っていた。まるで、自分の内の秘密を確かめるような手つきだった。
私はその場から視線を外し、自分のデスクへ戻るふりをしながら、その光景を頭のなかで振り返った。彼女が身につけている布は、昼職の光よりも、別の時間帯の灯りに似合うだろう。その時間帯の灯りのもとで、その布がどのように見えるか、彼女はどこまで想像して選んでいるのか。
夕方近く、外回りの予定をひとつ終えてオフィスに戻ると、空にはすでに薄い夕暮れの色が滲んでいた。十二月の空は暗くなるのが早い。窓の外のビルの輪郭は、昼間よりもはっきりと浮かんでいる。私は自分の席に座り、モニタに映るチャートを眺めた。赤い線は、午前中よりもさらに深く沈んでいる。電話越しの声は少し荒く、オフィスの空気は重たくなっていた。
そんなとき、スマートフォンが震えた。画面に表示されたのは、彼女の名前だった。「今夜、少しお話しできませんか」という一行だけのメール。句読点も顔文字もない。だが、その「少し」という言葉の置き方に、昼間とは違う層の空気が含まれていた。
私はすぐには返事しなかった。数分ほど放置したあと、短く「二十時なら」と打つ。彼女からの返答は早かった。「わかりました」とだけある。その素っ気なさが却って、彼女がこの約束に割いている時間の量と、そこへ持ち込もうとしている気配の濃さを教えてくれる。
仕事を終え、ビルを出る。十二月の夜の空気は、昼よりもさらに温度を下げていたが、どこかで湿り気も増している。街路樹には白い電飾が巻かれ、一定の間隔で点滅していた。赤と緑の数字が並ぶ画面は、今この時間もどこかで人間の心拍を左右しているのだろう。私はそれに背を向け、ホテルのロビーへ足を向けた。
ラウンジバーに入ると、柔らかな照明と低い音楽が、外気と別の温度で空間を満たしていた。窓際の席に目をやると、彼女が座っているのが見えた。コートは椅子の背に掛けられ、その下から覗くワンピースは、深い藍色に近いグレーだった。布はほどよい厚みがあり、身体に添いすぎず、離れすぎもしない。首元は浅く開き、鎖骨にうっすらと影を落としている。ワンピースの胸元に、装飾は何もなかった。だが、布の下でほんのわずかに高くなっている輪郭と、そのすぐ下で光を吸い込むように沈んでいる影を見れば、別の布が重ねられていることは明らかだった。
彼女が脚を組み替えたとき、ワンピースの布が太腿にゆっくりと沈み、布の沈みとともに、夜を吸い込むような影が、光を静かに奪った。その影は、昼の光とは異なる粘りを持って、影の底で冷たく反射して、夜の静かな深さを帯びていた。裾の奥で AGENT PROVOCATEUR のレースが花弁を深く重ねたような影を薄く覗かせる。細い糸の光の粒だけがバーの柔らかい照明に触れて、夜の光を散らすように揺れた。黒に近いワインレッドの色は、いっそう深まり、光を拒む層として沈んでいく。ガーターベルトの細い線が、影の深さの底で、ごく淡く浮かぶ。彼女の太腿に添って影が動くと、その影の厚みが、弦のように張られた締めつけの気配だけを残す。彼女が脚をわずかに動かすたび、締まったところにだけ影が深く落ちる。
彼女は何事もないようにグラスを持ち上げる。指先が細い脚をそっと挟む。彼女の指の動きに合わせて胸元の影が浅く揺れ、その揺れの淡さが、布の下に重ねたレースの細さと夜の空気を薄く包む。影は沈まない。沈まずに、ただ静かに伸びていく。
私は手首を動かして Reverso を裏返す。裏面は光を吸って、静かに沈む。時計は語ることをやめ、その沈黙が、彼女の内へ沈むレースの細さと同じ高さに重なる。時計の沈黙が、夜を深くする。彼女が見せる AGENT PROVOCATEUR の影の深さと、私が裏返した Reverso の沈黙の硬さ。ふたつの層が同じ高さで重なったところから、夜は静かに始まる。夜は、ただ光の粘度が変わるようにして訪れる。
私は向かいの席に腰を下ろし、ウイスキーを注文した。琥珀色の液体がグラスに注がれるあいだ、彼女は窓の外の街を見ていた。ビルの窓の光がいくつも連なり、そのあいだを車のヘッドライトが滑るように抜けていく。その光景を映すガラスに、彼女の横顔が薄い影として寄り添っている。輪郭は定まらないのに、その周りだけが、かすかに柔らかな影を抱いていた。
彼女のバッグは小ぶりで、テーブルの脇にきちんと置かれている。ふとした拍子に、バッグの口が少し開く。見えたのは、オフィスで見たものとは別の箱だった。ワインレッドの箱で、中央に控えめなロゴが刻まれている。箱の端がわずかに擦れていて、何度か手に取られたものと判る。彼女はそれにさりげなく指を添え、バッグへ押し戻した。表情には何の変化もないが、その指先には、自分が触れているものの質感をよく知っている者の慎重さがあった。
ワインレッドの箱には、おそらく同系色のランジェリーが収められているのだろう。柔らかなサテンに、細かく織られたレースが重ねられ、胸のカーブに添うように花弁の模様が配されているような。それぞれの花弁の中心にはごく小さな刺繍の点があり、光を受けるたびに目に見えぬほどの光の粒を返す。ストラップの幅は細すぎず太すぎず、肩に食い込まないほどにつくられている。前中心の小さなリボンは、単なる装飾というよりも、両側から布を引き寄せるための小さな結び目であり、その結び目の締まりによって胸のかたちがわずかに変わる。
それを身につけてここに座っているのか。それとも、まだ箱に入っているのか。私には判らない。ただ、彼女の胸元に落ちる影と、布の表面に浮かぶ微細な模様を見ていると、どちらにせよ「選ばれた布」であることだけは確かだった。
私たちは多くを話さなかった。仕事の話はいくらでもできるが、今日はそれを拡げる気になれなかった。彼女もまた、自分から話題を振ることはせず、問いかけには短く答える。沈黙が訪れても、それを破ろうとする焦りは互いになかった。沈黙が長く続くあいだ、彼女はグラスの脚をゆっくりと回し、その動きに合わせて、ワンピースの胸元の布がほんのわずかに揺れた。
窓ガラスには、街の光とともに、店内の光景も薄く反射している。そこに重なる彼女の姿は、実際よりも少し暗く見え、その暗さが逆に輪郭を際立たせていた。首から肩にかけての線、ワンピースの布が腰のあたりでほんの少しだけ絞られ、そこから緩やかに落ちていく線。椅子に座るとき、スカートの裾が膝にかかる位置。そうしたものがすべて、夜の光のなかで少しだけ誇張されて見える。
私はウイスキーをゆっくりと飲みながら、彼女と距離を測っていた。仕事上の距離と、こうした場の距離は、似ているようでいて違う。どこまで踏み込めば、相手の均衡を崩さずにこちらの意図を通せるか。その見極めには多少の時間を要するが、ひとたび見極めてしまえば、あとは同じ幅で歩き続ければいい。
彼女はこちらを見ない。窓の外の街を見たり、手元のグラスを見たりしている。その視線の動きを追っていると、ふと、彼女のまぶたの際にわずかな陰りが増したように見えた。疲労か、不安か、期待か。どれも完全には消えていない。その混ざり合ったものを、自分の都合のよいように解釈することが、私の癖でもあり、仕事でもある。
やがてグラスが空に近づいたころ、私は時計を見た。針の位置は、このまま終電を心配するにはまだ早く、しかし何事もなかった顔で解散するには、少しばかり遅い時刻を指していた。私は伝票を手に取り、席を立つ。彼女は驚いたように目を瞬かせ、それからコートを取り、静かに袖を通した。
コートの下でワンピースの布が身体に密着して、ランジェリーのレースの縁が布の裏に小さな影をつくる。その影は誰の目にも触れないが、自分が何を身につけ、どこに重ねているかを知っている者には、はっきりと感じ取れるはずだ。彼女の指先がコートを留めるボタンに触れるとき、その指は、自分の身体を包む布の層をひとつずつ数えているようにも見えた。
エレベータへ向かう廊下は、厚い絨毯が敷かれ、足音をほとんど吸い込んでいた。壁際のランプが一定の間隔で置かれ、それらが暖色の光で空間を染める。彼女は私の半歩ほど後ろを歩いていた。その距離は、オフィスのものよりも曖昧で、知らない誰かが見れば、同僚かもしれないし、そうでないかもしれない、と判断に迷うだろう。
エレベータで、私たちは向かい合わなかった。彼女はドアのほうを向き、私は階数表示のランプを見ていた。密閉された空間に、互いの呼吸と、衣擦れの音だけがある。ワンピースの布が膝のあたりでわずかに擦れる音は、耳で聞くというより、空気の密度の変化として伝わってくる。その変化はほんのわずかなのに、足元の安定を揺らすほどにははっきりしていた。
十二月八日は、始まりの日である。世界を巻き込んだ大きな流れの始まりであるとともに、個々の人間の足元の影のかたちが変わり始めた日でもある。誰かが旗を掲げたから始まったのではなく、誰かが何かを読み上げた瞬間、もう元には戻れない線を越えてしまっていた、という始まり。この密閉された箱で、階数を示す数字がひとつずつ増えていくのを見ていると、その感覚が身体のどこかに薄く甦る。
扉が開くと、冷たい廊下の空気が流れ込んできた。外の世界のあいだに引かれていた境界が、乾いた音を立てて切れるような気配がある。私たちは同じ方向へ歩き出し、ホテルのロビーを抜けて外へ出た。
夜の街は、昼職のそれと同じ構造を持っていながら、別の顔をしている。ビルの窓の灯りは点々と残り、道路には車の列が伸びている。歩道を行き交うひとの数は昼より少ないが、その一人一人が、昼とは違う表情のように見える。私たちは駅と逆の方向へ歩き出した。互いにそのことをはっきりと言わないまま、足だけがそちらを選んでいる。
彼女のヒールは、アスファルトに一定の音を刻んでいた。その音がときどきわずかに乱れる。その乱れは、たぶん歩道の小さな段差や温度のせいなのだろうが、そのたびに、彼女の内でなにかの重さが前後に揺れているような錯覚を呼ぶ。コートの裾がふわりと揺れ、その下に潜むスカートの布が、さらにその下の布と擦れ合っている。
この夜が、どこで終わるのか決めているのは、私なのか、彼女なのか。あるいは、今日という日付そのものなのか。始まりというのは、選ぶというよりも、気づけばそこにいるという感覚に近い。私は歩きながら、自分の影と彼女の影が、街灯のもとで重なり合っているのを見ていた。それは、二人分でありながら、ひとつのかたちに見えなくもない、そんな重なり方だった。
十二月八日の夜風は冷たい。だがその冷たさの奥で、別の温度が静かに高まりつつあることを、私は自分の掌で感じていた。それは、歴史の教科書に載るような熱ではない。ただ、ひとりの女の選んだ布の織り目と、ひとりの男の視線の行き先が、今日という日付に初めて交差した、その小さな熱だった。
その夜の終わり方を、私はいまでもはっきり思い出せない。どこを曲がり、どの信号で立ち止まり、どの角で別れたのか。細かい道は霧のように曖昧なのに、途中に挟まれた幾つかの断片だけが、やけにくっきり残っている。横断歩道の白線で彼女のコートの裾が風に捲れかけたとか、自動販売機を通りかかったとき、缶の並ぶ光のなかで、彼女のヒールの先が躓いた音とか。そういう些末なものだけが、出来事の輪郭を照り返すように、記憶の底で長く光っている。
ただひとつだけ確かなのは、その夜を境にして、彼女にたいする距離が、元の位置には戻らなくなったということだ。翌日、オフィスで顔を合わせたとき、私たちはいつもどおりの挨拶を交わし、事務的な会話を済ませ、周囲の目から見て何ひとつ変わっていないようにふるまった。彼女のスーツも、膝丈のスカートも、ブラウスの色も、前日とそう違ってはいない。ただ、会議室のガラス越しに彼女の横顔を見たとき、その頬に落ちる影の濃さが、以前と違っている気がした。光源の問題ではなく、影そのものが、内から色を増したように見えた。
数日後の面談のとき、彼女は少し違う組み合わせで現れた。ジャケットはいつもより濃いチャコールグレーで、スカートはそれより半トーンだけ明るい色。同じ地味さのなかで、ごくわずかに濃淡をずらしている。ブラウスは相変わらず淡いクリーム色だが、その布の下で、胸元のカーブを支えるものが以前より明確な線を持っている気がした。椅子に座るとき、布の落ち方が滑らかで、余計な皺を作らない。布の下に余裕が少ないせいで生まれる、独特の均整があった。
彼女は書類に目を落としながら、淡々と状況の変化を伝えた。元夫とのやりとり、実家の反応、職場の空気。内容だけ見れば、さほど劇的なものではない。だが、話すあいだ彼女の指先は、ペンの胴を細く撫でるように動き、時折、胸元の布を押さえるようにそっと触れた。その触れ方は、襟の乱れを直すというよりも、内側の布の位置を確かめるためのものに近かった。自分の身体に巻きつけた「構造物」を、掌を通じてなぞる仕草。彼女の指先は、そこにどのような織り目が重なり、どのような締め付けがあるのかをよく知っている者のものだった。
私には、彼女が私を頼ってきているという事実と、私がそれを利用しているという事実が同時に見えていた。相談事の多くは、こちらの用意した枠のなかに収めることができる。彼女の生活を守るためという名目で、数字の配列や契約の行を整えて、その見返りとして、彼女の時間や視線や沈黙が、こちらの手元に溜まってゆく。それを不均衡と感じないのは、彼女の側にもまた、私を自分の物語に組み込もうとする意図があるからだろう。
ランチタイム、オフィスの隅の給湯室で彼女がコーヒーを注いでいるのを見かけた。私は声をかける代わりに、少し離れた場所からその背を眺める。明るい蛍光灯のもとで、ジャケットの背には、先日見たのと同じ浅い凹みが横に走り、その凹みの上端で、布がわずかに盛り上がっていた。フックが止まり、バンドが締められている。その線は、彼女の背骨とは別の意味で、身体の中心を示していた。
彼女はコーヒーを持ち直しながら、左肩をほんの少しだけ後ろへ引いた。その動きに合わせて、ジャケットのなかでストラップが布越しに動く気配がある。わざとではない、無意識の仕草。だが、無意識のほうがむしろ本音に近いこともある。内側の布にふと意識が向かったとき、その動きの周りの空気だけが密度を変える。私はその変化を、自分の胸の温度のわずかな上昇として受け取っていた。
仕事の日々は、数字の波に従って上がったり下がったりしながら、しかし着実に前へ進んでいく。為替はさらに円高へ振れ、株価の赤はしばらく画面から消えなかった。そんななかで、彼女の面談だけが、数字と別の尺度を持つ時間として、私の一週間に挟み込まれていった。
夜の約束が二度、三度と重なるうちに、ホテルのラウンジのソファは、私たちにとって特定の温度を持つ場になっていった。彼女の服装はいつも大きくは変わらない。地味なスーツ、控えめなワンピース。しかし、その下に纏う布の選び方は、少しずつ変化を見せているようだった。ある夜、彼女が身につけていたのは、黒に近いインクブルーのランジェリーだったのだろう。それは、胸元に落ちる影がいつもより深く、布に浮かぶ模様が、光を吸い込むように沈んで見えたからだ。レースの花弁は同じでも、糸の色が変われば影の質も変わる。その変化に、彼女自身がどこまで自覚的なのかは分からない。ただ、少なくとも、自分の内に重ねた布の選択が、誰の目にも触れないまま、その夜の空気を濃くしていることだけは確かだった。
私たちの会話は相変わらず多くはない。互いの生活について、いくつかの説明だけを交換して、その合間を長い沈黙が埋める。沈黙のあいだ、彼女はグラスを指でゆっくりと回し、私は彼女の手元を観察している。グラスの脚を挟む指は細く、その指が冷たいガラスと交わる角度に、慎重さがある。指先に、内側の布の織り目が染み込んでいるようだった。布の繊細な凹凸に触れている指は、その記憶を忘れない。ガラスの滑らかさに触れているときでさえ、その滑らかさを、内に隠したものの繊細さと同じように測っているように見える。
ある晩、彼女は少し遅れてラウンジに現れた。コートの下から覗くワンピースは、これまでのものよりも光沢を帯びていた。色は深いグリーンに黒を混ぜたようなもので、照明の角度によって、緑にも灰にも見える不確かな色だ。椅子に腰掛けるとき、スカートの布が太腿に添って静かに落ち、その落ちた先で、脚に巻きついたストッキングがわずかな艶を返した。その艶は、昼間のオフィスでは決して許されないものだった。
席に着いた彼女は、いつもより少しだけ口数が多かった。仕事の愚痴をこぼすでもなく、誰かを責めるでもなく、自分の置かれた状況を静かに俯瞰するような話し方。それを聞きながら、私は彼女の言葉よりも、言葉を乗せている声の高さと、そこに混じる微細な揺れに注意を向けていた。声の奥には、何かを諦めた者の静けさと、何かを手に入れようとしている者の熱が、妙な均衡で同居している。
話が少し途切れたとき、彼女はふと自分の胸元に視線を落とした。ワンピースの布がそこだけほんのわずかに動き、その動きに合わせて、レースが布越しに影をつくる。花弁のレースの一片が、薄い布で天井の光を受け、わずかに浮き上がって、すぐに沈む。私の視線がそこへ向かうよりも先に、その動きそのものが私の注意を引いていた。彼女は自分の指でさりげなく胸元の布を押さえ、何事もなかったようにまたグラスへ手を伸ばす。その一連の仕草に、「見せない」と「隠しきらない」のあいだの均衡があった。
私はその夜、彼女の選び方について、少しだけ理解が深まった気がした。彼女は、自分の内の布を見せびらかすことはしない。だが、見えなくするわけでもない。外側の地味な殻と、内側の精妙な織り目とあいだに、わずかな隙間を残して、その隙間から漏れ出る気配こそ、自分の存在の核としている。私がそれに気づいていることを、彼女はおそらく知っている。そして、私が気づいていることを知ってなお、その選択を続けている。
十二月はいくつかの夜を費やして、静かに深くなっていった。街のイルミネーションは日ごとに輝きを増し、オフィスの会話には年末の予定や、賞与の金額という話題が混じるようになる。だが、私にとって重要なのは、カレンダの数字のなかでも、あの八日の持つ感触だった。始まりの日付としての冷たさは、時間が経つほどに薄れるどころか、むしろ積み重ねられた出来事によって、静かに厚みを増している。
私はときどき、自分が彼女の関係をどこまで制御できているのか、逆にどこまで制御されつつあるのか考えた。彼女にとって私は、生活を整えるための道具であり、夜のうちに自分の「女性」を確かめるための鏡のような存在なのだろう。私にとって彼女は、自分の観察眼と判断力を試すための対象であり、自分の支配を測るための尺度でもある。互いに相手を利用しようとしているが、その利用がいつの間にか逆転して、境界が曖昧になっていることを、どちらもはっきりとは口にしないまま、ただ、静かに受け入れている。
ある夜、ラウンジではなく別の店で会おうということになった。彼女が提案したのは、小さなビストロのような店だった。ビルの二階、目立たない階段を上がった先にあるその店は、木のテーブルと薄暗いランプの柔らかな陰影のなかに沈んでいた。窓は小さく、外の光景はほとんど見えない。そのかわり、店内の空気は濃く、グラスや皿の音、低く抑えられた笑い声といったものが、すべて同じ温度で混ざり合っている。
彼女はその夜、黒に近いダークブラウンのワンピースを着ていた。布地には細かなヘリンボーンの模様が織り込まれていて、光の加減で筋が現れたり消えたりする。首元はやや詰まり気味で、鎖骨はほとんど見えない。そのかわり、胸元から腰のラインがなめらかに強調されていた。布の下には、きっとそれに合わせたランジェリーが選ばれているだろう。黒に近いワインレッドか、あるいは深いプラムか。レースの模様は花弁ではなく、もっと抽象的な蔦のパターンかもしれない。布そのものの織り目が複雑であるほど、その上に重ねられるレースは、むしろ単純なかたちを好むことを、私は知っていた。
料理が並び、ワインが注がれ、店内のざわめきが一定の高さを保ったころ、彼女はふいに手首の時計を外した。ベルトの跡が薄く肌に残り、そこにランプの橙色の光が滲む。時計をバッグにしまうとき、コートの内ポケットから、例のワインレッドの箱が一瞬だけ顔を出した。彼女はそれを、まるで何でもない小物であるかのような手つきで押し戻す。私の視線がそこに向かうのを、彼女は当然のこととして受け止めているようだった。
その夜、私たちは店を出たあと、いつもと違う方向へ歩いた。駅へ向かう道ではない、ビルとビルの隙間へ入り込むような狭い通り。そこには、古びたビルの入口や、小さな看板がいくつか並んでいた。彼女は足を止め、ふと私のほうを見た。はじめて真正面から視線がぶつかる。彼女の瞳の奥には、不安とも期待ともつかない色が浮かんでいたが、そのどちらも完全には支配していない第三の色があった。
私は、その視線を受け止めながら、自分がここでどちらの方向を選ぶかによって、彼女の関係の線がはっきりと折れ曲がることを理解していた。あの朝の一報が、世界の線を変えたように。始まりというのは、そういう瞬間の連続からできている。後戻りができないという意味の始まりではなく、戻るという選択そのものが、もう意味を持たなくなるという類の始まりだ。
結局その夜、私たちはビルのエレベータに乗り、無機質な廊下を歩き、鍵のかかる扉の前で短い沈黙を共有した。その先に何があったか、ここで細かく記すつもりはない。重要なのは、その扉を開ける前と後で、彼女のランジェリーの意味が変わってしまったということだ。以前までは、それは私の視線と想像だけで完結する「見えない構造物」だった。扉の先で、それははじめて「触れないまま知ってしまったもの」から、「触れたことのあるもの」へ姿を変えた。
それからの日々、彼女は相変わらず、昼には地味なスーツに身を包み、夜には選ばれた布を纏って現れた。私たちの関係は外から見れば、少し親しい相談相手にしか見えないだろう。だが内から見れば、彼女の選ぶ織り目の変化と、私の視線の行き先の調整が、絶えず互いを読み合っていた。彼女は自分の「女性」を充分に知り、その活かし方を学んでいたし、私はそれを利用しながら、自分自身もまた利用されていることを、どこかで冷たく観察していた。
十二月八日から始まった線は、その後も静かに伸び続けた。カレンダーの日付は変わり、年が明け、季節が巡っても、そのとき足元で折れ曲がった影のかたちは、元には戻らない。戻れないからではなく、ひとたび別のかたちを知ってしまった影にとって、元のかたちがもはや意味を持たなくなってしまったからだ。彼女がどんなランジェリーを選ぼうと、どんなスーツでそれを覆おうと、私たちのあいだにある「始まり」は消えない。その始まりは、世界のどこにも記述されない。ニュースにも載らず、記念日にもならない。ただ、ひとりの女の選んだ布の織り目と、ひとりの男の視線の行き先が、ある冬の日に初めて交差した、その事実だけが、私のなかで静かに残り続けている。