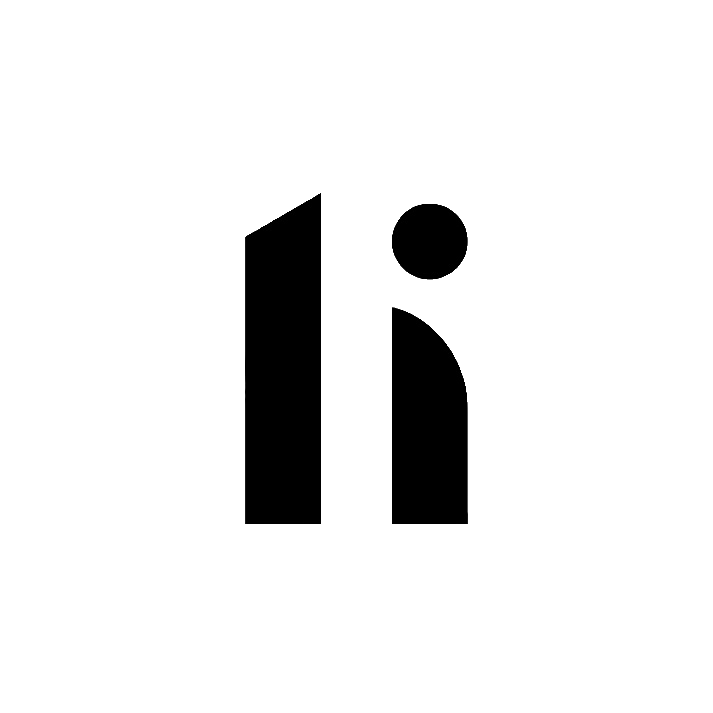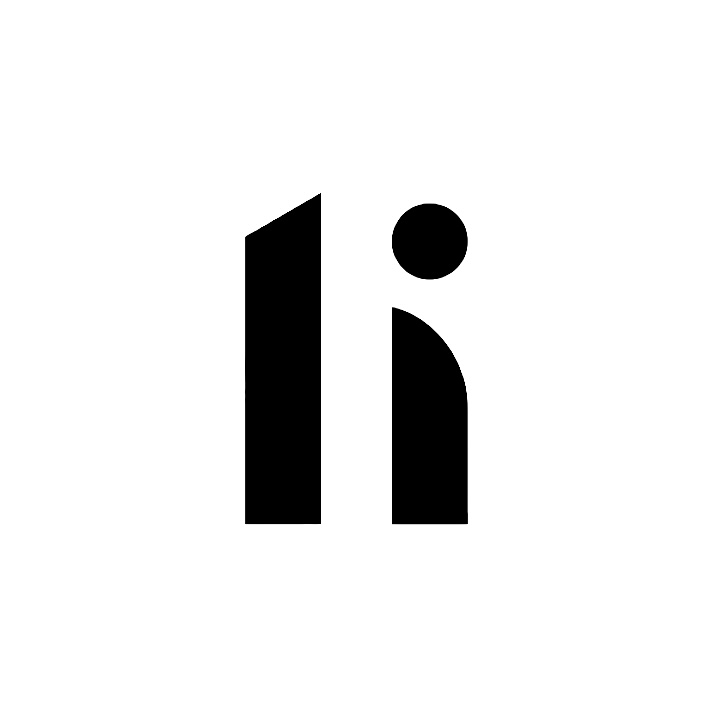ひさしぶりに彼女から連絡があったのは、月曜の昼だった。画面の隅に、小さく名前の頭文字だけを示す通知が灯り、じりじりとした会議の終わりかけに、そこだけ別の温度の気配を差し込んできた。
——今週のどこかで焼鳥
それだけの短い文だった。句読点も絵文字もない。あまりに素っ気ないので、誤送信とさえ思った。
私は、会議室の空調の低い唸りを聞きながら、その一行を眺めた。画面越しにも、文字の置き方に癖が残っている。学生のころ、プリントの余白に書いていた走り書きに、その癖がつながっているのが解る。
——いいね。水曜か木曜。
とだけ返す。しばらくして、日時と駅名が送り返されてきた。その間合いの取り方も、昔から変わらない。必要な情報だけを、余計な飾りをつけずに渡してくる。その素っ気なさが、むしろ親密の証のように思えた。会議を締めくくって画面を閉じると、部下たちがラップトップを閉じる音が連なって聞こえてくる。
私と彼女は、大学の同じサークルにいた。長く続く関係ではなかったが、一度は付き合っていた。互いに不器用で、不必要に真面目で、互いに線を引き合った。何かが起こりそうな夜には、わざわざ何も起こらないように、あらかじめ二人で決めてしまうようなところがあった。
ほどなくして自然と別れ、そのあとも大人数で集まるときは顔を合わせ、なんとなく友人として話すようになり、卒業してからも、年に数回は呑みに行く仲になった。互いに恋人ができては消え、消えてはでき、気づけば三十代の半ばまで、添い遂げる誰かと暮らすこともなく過ぎていた。
仕事は、それぞれ順調だった。彼女は華やかな会社で企画をまかされ、私は地味な業界で数字と人事を組み替える仕事に就いて、それなりに重い責任と権限を預かるようになった。
同窓会で、誰に二人目の子が産まれただの、マンションを買っただの、そんな話を聞くたびに、彼女と私は、短いメッセージを交わした。
——また、みんな順調に大人になっていく。
——私たちは、いつまで学生の延長なんだろうね。
そんな他愛のないやりとりを、適度な距離と頻度で続けてきた。
それが、ある日をもって「焼鳥」という単語に変わった。レストランでもなく、ワインバーでもなく。彼女がそこを選んだのは、おそらく無意識のうちだろう。だが、その無意識が、今の彼女の気分をいちばん正直に表しているように思えた。
指定された駅で降りると、まだ夜が始まるばかりの時間だった。仕事帰りのひとたちが一斉に吐き出される改札を抜けて、雑居ビルの並ぶ通りを歩く。新しい店と古い店が、乱雑に肩を並べている。光の強さと看板の古さが揃わず、どの店が生き残り、どの店が消え去るのか、一目ではわからない。
路地をひとつ曲がると、空気の匂いが変わった。排気ガスの残り香と湿ったコンクリートの匂いに、急に炭火と油の匂いが混ざり始める。
「そこ」という短いメッセージとともに、店の写真が送られてきた。白い暖簾に黒い文字。古びた木の引き戸。実物は写真で見るよりもわずかにくたびれていたが、そのくたびれ方は嫌いではない。
戸を引くと、立ち上る煙が目元までふわりと押し寄せた。炭に脂が落ちる音が、狭い店内に細かく震えて散っている。焼き台で主人が串を返すたび、ぷっくりと膨らんだ肉が、照明を受けてつやつやと光る。膨らみきった皮のあいだから、透明な脂がひと粒、またひと粒、網に滴り落ちる。
視線を巡らせると、カウンタの中央あたりに、彼女の横顔があった。濃いチャコールグレーのパンツスーツ。ジャケットは、痩せているというには充ちすぎた身体に、きちんと寸法を合わせて仕立てられているらしく、肩から背中にかけて、布が内側の厚みを受け止めて、静かな丸みをつくっていた。
下に着けた白いブラウスの生地は、店内の灯りを柔らかく吸って、うっすらと奥を透かしている。その奥で、胸の丸みが、光の濃淡だけで輪郭を示していた。胸元のボタンは上から二つ留まっていて、そのすぐ下の一点だけが、彼女の裁量で外されている。その小さな隙間から、肌と布のあいだに落ちる影が、細い谷のようにすっと伸び、その奥に、もう一枚の薄い布の端が、ごくかすかに光を返した。
よく目を凝らさなければ見逃してしまうような、淡いレースの縁だった。繊細な糸で編まれた飾りの線が、布の奥で静かに波打っている。学生のころに彼女が身につけていたのは、たいてい綿の、色気という言葉から遠い下着だった。黒か、水色の、洗濯を重ねて少し頼りなくなった布。その素っ気なさを私は知っている。今、胸元のわずかな隙間から覗いているものは、あのころの布とは明らかに別物だった。布地そのものが、見えないところで誰かに見せるために仕立てられている類のものである。ブラウスのボタンのところで布がわずかに引かれ、動くたび、そのレースらしきものが影と入れ替わりながら、呼吸の鼓動に合わせて、ごく静かに出入りしている。
パンツは、腰から腿にかけて、布地が波打たぬほどの細さで仕立てられている。椅子にかけた姿勢のせいで、生地が腰のあたりからそっと引き上げられ、その下にあるもののかたちを誇張することなく拾っていた。尻から腿へ続く曲線を布がなぞり、それから椅子の座面に添って、なだらかに落ちている。
私は彼女の斜め後ろに立って、軽く手を上げるだけで合図する。彼女はこちらを振り向き、煙の向こうで、目だけで笑った。
「そこ、空いてるから」と、顎だけで隣の席を示す。声の調子は、昔より少し低くなっている。その低さの奥に、日々の会議室で研ぎ澄まされた理性と、そこから零れ落ちた疲労が、薄い層になって重なっているように聞こえた。
私はジャケットを脱いで椅子の背に掛けて、彼女の隣に腰をおろす。そのとき、彼女の腰と椅子のあいだから、パンツの布がこすれる微かな音が聞こえる。椅子の木と、生地と、その下にあるものが、今日のかたちを相談し合うような、短い音だった。
カウンタの木は、長年の手垢と脂でしっとりとした光沢を帯びている。焼き台では、ねぎまの白い葱が焼けしずみ、そのあいだに挟まれた肉が、むっちりとした厚みを保ちながら色を変えていく。脂が浮き、きゅっと締まり、それからしっとりとした艶になるまで、私は無意識に目で追っていた。
「とりあえず生でいい?」彼女が主人に目を向ける。その一言で顎がわずかに上がり、首筋から顎にかけて、肌の張りと影が一息に露わになる。そこには、よく笑い、よく喋り、よく働いてきた者の、充実した厚みがあった。
ジョッキがふたつ置かれ、泡の高さが揃えられる。彼女は軽くグラスを持ち上げ、そのまま私を見た。その仕草に連れて、胸元の布がわずかに持ち上がり、その下に隠れたものが、わずかな遅れをもってかたちを変える。布の下の動きは、そのまま皺となって表面に現れ、ブラウスの一部を、ほんのわずかにふくらませた。焼き網で串を返された肉が、遅れてぷるりと震える。
「はいはい」と私は言い、ジョッキを合わせる。その音が、焼き台の火と混じり合って、店の空気の一部になった。
ビールの苦味が喉を滑り落ちる。皮の串が焼き上がる。串先から尾のほうへ向かって、皮がぷっくりと膨れ、ところどころに透明な脂の珠が溜まっている。主人がそれを塩に載せると、脂が皿の白に小さな円を描くように滲んだ。
最初に皮を取ったのは、昔と同じく彼女だった。指先で串をつまみ、歯を近づけるまえに脂を目で確かめる。むちりと詰まったところに、前歯をそっと立てると、薄い皮の膜が音もなく裂け、熱い脂がにじみ出る。噛み締めたとき、皮と肉の境目で、しっとりとした抵抗が舌を押し返し、それからゆっくりとほどけていく。それを彼女はいつもの淡々とした顔のまま受け止めていた。喉を通していくときだけ、首筋の筋肉が、わずかに動くのが見えた。
その喉の動きと、ブラウスの隙間からのぞくレースの端を、私は同じ時のなかで見ている。かつて彼女のシャツの下に見えていたのは、装飾らしい装飾もなく、ただ身体を覆うための無造作な布にすぎなかった。今、胸元で控えめに光る細工の縁は、その布と別の時を経て、別の選び方で身につけられたものと告げていた。
仕事に熱心でいるうちに、女の肉体のほうは、静かに熟れていたのだろう。削られたのは頬の影であり、膨らみを増したのは、布の下に隠れているところだった。皮がちょうどよく脂を溜めて火で膨らむように、痩せ切らず、きちんと重さを湛えている。
彼女が串から肉を外すとき、唇に触れた脂が、薄く光を残す。それを舌で拭い取るでもなく、紙で拭き取るでもなく、そのままビールで流し込む。その無造作が、かえって肉をきちんと受け容れている感じを強くする。
隣に新しい客が座り、カウンターの幅のわりに人の肩が増えたせいで、私と彼女のあいだの間隔が詰まる。彼女が少しだけ体をこちら側へ寄せた。意識してか無意識か、そのわずかな動きが、椅子の脚と脚のあいだに残っていた空間を埋める。
膝の少し上あたりで、布越しに柔らかなものが触れた。パンツに包まれた彼女の腿と、私の腿が、線ではなく面で、静かに接する。押し当ててくるというほど強い力ではない。むしろ、互いの重さが自然に凭れて、そこがもっとも近いところになった、と言い訳のできるほどの重なりだった。
しかし、肉と肉が布を一枚隔てて触れたときの、あの生きたものの温かさは、言い訳と別のところでこちらの感覚に届く。焼き台で、串と串が並んで焼かれているうちに、端の肉片がいつのまにかくっつきあっている。
彼女は、自分の腿が触れたことに気づいていないふりをしているようにも見えたし、わざと気づいていないふりをしているようにも見えた。視線は相変わらず焼き台の火のほうを向いている。だが、一度だけ、太腿の筋肉が微かに張って、すぐに力を抜くのが伝わってきた。私は、腿が触れたところを動かさないようにして、ジョッキを持ち上げる。冷たいガラスの感触と、膝の温かさが、身体のなかでまったく別の系統として存在している。
「しかしまあ、こうして平日に焼鳥屋で脂まみれになってるなんて、私たち、立派な悪友だよね」
彼女が、皮の串を半分ほど齧ってから言った。
「悪友ね」
私は短く答える。
呼ばれた側として、その言葉は案外、心地よい。責任も期待も、半分ほど軽くなる。けれど、腿が触れたままの状態で「悪友」と口にすると、その言葉の輪郭が、少しだけぼやけるのを感じた。
串から外した肉を口に運ぶたび、その動きに合わせて、彼女の腿の筋肉が布の下でわずかに動き、そのたびに、触れているところの感触が細かく変わる。焼き網で肉がじりじりと火を受けながら、脂の玉がじわじわと増えていく。
皿には、食べ終えた串だけが増えていく。木肌には、焼かれた肉の脂がまだしっとりとまとわりつき、指でつまめば、かすかなべたつきが爪の先に移りそうだ。そのべたつきは、店を出てからもしばらく指先に残るだろう。彼女と私の髪や服に染みついた煙の匂い、そして今、布越しに触れた腿の温度の記憶のように。
閉店の時間が近づき、店の空気がゆっくりと冷めていくにつれて、焼き台の熱を吸って輝いていた肉の艶も、皿で落ち着いた色へ変わっていく。客が一組、また一組と立ち上がるたび、煙の層が薄まり、代わりに衣服に染みついた脂の匂いだけが、自分のまわりで、かすかに温かさ持って残っていた。
勘定を済ませるために少し身体を引いたとき、腿と腿の接点がほどける。そこだけ急に風が通ったように感じて、自分の皮膚が、その喪失をはっきりと意識しているのがわかった。
彼女は椅子で姿勢を直し、腰を軽く持ち上げる。そのわずかな動きで、パンツの布が尻の丸みに引かれてぴんと張り、布のなかでひろがった肉が、椅子にやんわりと沈む。張りと沈みのあいだに生まれる、ほんの短い間隙。その間隙そのものが、彼女の肉体が歳月と仕事で熟してきた証のように思えた。
日々の会議室では、彼女はその重みをうまく隠しているのだろう。だが、こうした椅子の微細な動きには、隠しきれないものがあった。腰のあたりで布越しにわずかに押し寄せては退く感触が、先ほどまで触れていた腿の温かさの名残と混ざり合う。焼き網の肉が、火に近づけられたり離されたりするたびに、表面が膨らみ、また縮む。
会計を済ませ、外に出る。夜風に触れた途端、彼女のスーツに染み込んだ煙の匂いが、静かにふくらんで立ち上がる。火のそばに長くいた肉が、皿に移されてもなお、温かさと匂いを失わないように。
駅へ向かう道を、歩幅を合わせて歩く。パンツの腿のところが、歩くたびにわずかに張ったり緩んだりして、肉が揺れる。その揺れは、焼き台で主人が串を返したとき、肉の端がぷるりと震えるのに似ていた。さっきまで自分の腿に触れていたところが、その揺れのたびに、記憶を擦られるように疼く。
路地を抜けて少し明るい通りに出ると、街灯の白い光が、彼女のパンツスーツの布地を、さきほどの店内と別の仕方で照らし出した。薄闇のなかではただの濃い色だったものが、光を受けて、ところどころで線に変わる。
腰の少し下、尻のいちばん高いところから腿にかけて、布の表面に、細い弧を描く影がいくつか浮かんでいる。パンツの縫い目ではない。布の下で走っている、別の布の縁。ヒップを横切る線と、斜めに落ちていく線が、重なり合って、淡い模様のように布の外へにじみ出ている。
それは、かつて学生時代に彼女のシャツに透けて見えた、平坦な綿の下着の輪郭とは明らかに違う線だった。あのころの布は、まっすぐで、角ばっていて、寸法ありきの線を引いていた。今、パンツの下に見える線は、どこかしなやかで、腰の丸みに添うようにして、布そのものが曲線を欲しがっているように見える。
歩くたび、パンツの布が尻と腿にぴたりと吸いついては離れ、腰骨のあたりできゅっと締まり、それからまた元のかたちに戻る。その動きにあわせて、下に隠れたランジェリーの縁が、布ごと微妙に位置を変えて、光の加減で現れたり消えたりする。
色そのものは見えない。だが、その線の細さと、弧の描き方と、腰のどの高さを通っているかという事情だけで、それが「ただの下着」ではなく、布そのものに装飾と意図をまとった類のものと知れる。
彼女自身が、その違いをどこまで自覚しているのかは判らない。仕事のスーツに合わせて選んだだけかもしれないし、そうではないかもしれない。ただ、布の下で変わってしまった線を、昔の記憶と照らし合わせて意味づけているのは、今この瞬間の私のほうだった。
「このあと、どうする?」と、私は問わなかった。「送ろうか」とも言わなかった。ただ、信号を待つ横断歩道の前で、二人あわせて足を止めた。
街灯の下、彼女の身体を横から見る。ジャケットの裾が腰で止まり、パンツが尻の高い位置から腿へ、ゆっくりと量感を増して落ちていく。昼間のオフィスでは直線的に見えるスーツが、今は、火のそばで温められた肉のように、ところどころで柔らかく膨らんでいた。尻の丸みの下がったあたりで、さきほど見えたランジェリーの線が、横からの光でまた細く浮かび上がり、すぐに闇に紛れる。
信号が青に変わり、ひとの波が歩き出す。だが、彼女は歩かず、そこに立ち尽くした。私も動かなかった。さきほどまでくぐっていた暖簾の脂の気配が、まだ背中にさざめいている。肉を串から外した後に指先へ残るべたつきのように、店の空気そのものが、まだ肌に貼りついているようだった。
通りには空車のランプを灯したタクシーが何台か流れている。ホテル街というほどあからさまではないが、いくつかホテルが点在している。焼鳥屋から帰る道として、理性の上では揃わないだろうが、気分の上ではあまりにも好ましい方向だった。
「……タクシー、あっちのほう拾いやすいよね」彼女が、ごくかすれた声で言った。単なる現実的な提案のはずなのに、その言葉が落とす影が、妙に長い。私は短く頷く。それだけで、歩き出す方向が決まる。
私たちは、駅の方向に逆らって歩き出す。焼き台の火から離れ、だがまだ身体の奥に熱が残ったままの肉のように、ゆっくりと余熱で動いている。
パンプスのかかとがアスファルトを叩く音にあわせ、パンツの布が、腿で柔らかく膨らみ、また沈む。尻の丸みは、歩くたびに布のなかで重心を移し、その重さがすべて、布の張りへ伝わっていく。肉の火入れが、ちょうどよい時分に達したときのような、しっとりとした落ち着きが、彼女の歩き方に広がっていた。そのたびに、腰のあたりでランジェリーの線が、布の下でわずかに動き、その線の存在を知っている者にだけ、揺れの跡を残す。
タクシーを止め、並んで乗り込む。座った拍子に、パンツの尻のところがぴんと張り、それから座面に押し広げられる。網に置かれたぼんじりが、火から離れて皿に乗せられたとき、熱を保ったまま、重みだけが柔らかく沈む、あの感じに似ている。
ホテルの車寄せに着いて、私たちは降りる。ロビーの空気は無臭に近く、さっきまで身にまとっていた煙の匂いが、いっそう濃く、自分の身体の近くに押し寄せてくる。
並んでエレベータを待つ。扉に映った彼女の後ろ姿は、昼間の会議室の「直線的な」姿とはまるで違い、パンツに包まれた尻と腿の量感が、照明を受けて静かに浮き上がっていた。腰の少し下で、ランジェリーの縁が、布越しにごく薄い影となって現われ、それがパンツの縫い目の線と交差して、短い弧をつくっている。焼鳥屋の火に温められ、煙の脂に包まれたままのような肉体。それを布がきちんと抱え込み、その抱え込み方が、熟れた肉そのものの輪郭と重なっていた。
エレベータが開き、扉が閉まる。狭い密室に、彼女の肉体の輪郭と、焼鳥屋の余熱のような匂いが、濃度を増して満ちてゆく。
パンツの腿は、立ち姿のぶんだけ布に余裕を得て、椅子に押し潰されていた肉が、静かにふくらみ直している。そのふくらみは、まるで、火から少し離されて休ませている肉が色を取り戻すような、そんな静かな「熟れ」の時間を思わせた。
悪友という言葉は、まだ私たちのあいだに残っている。けれど、焼鳥屋という場にいったん身を浸した肉体は、その言葉の境界を、そろそろ曖昧にしつつある。
エレベータが上昇を始める。その揺れとともに、彼女の尻の肉が柔らかく揺れ、揺れたところがパンツの布のなかに、しっとりとした温度を残した。その温度が、こちらの意識のほうへ先に届いた。