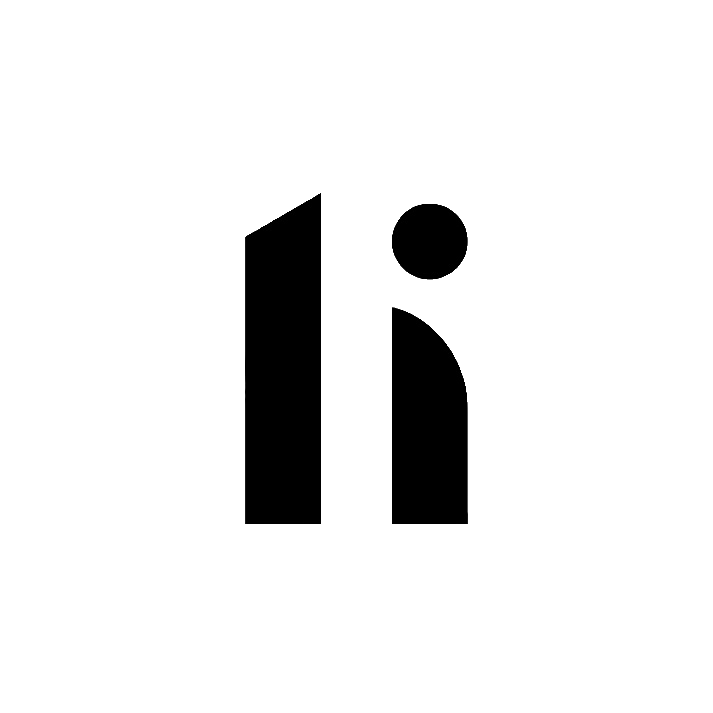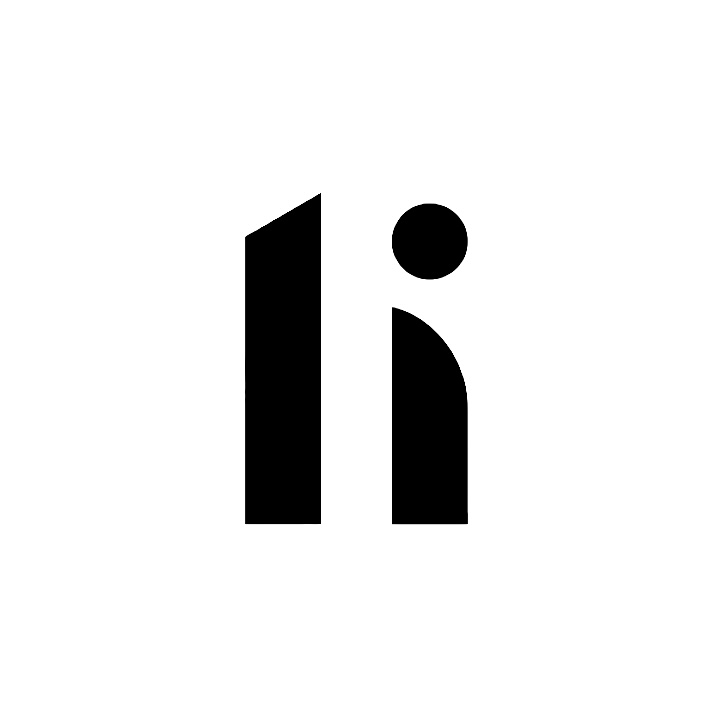十二月のはじめの空気は、冬そのものにしてはどこか頼りなく、しかし秋の残り香はすでに消え、ただ冷たさだけが先走って街を覆っていた。会社のビルを出て、ほっと息をつくまもなく、交差点の赤信号が私を立ち止まらせた。人々はそれぞれの家路へ急ぎ、風に襟を押しつけるように歩いている。その人混みの端に、白いレジ袋を提げた女が静かに立っていた。
レジ袋は、閉じられているとは言えなかった。ひと結びはしてあるものの、指先の力がほんのわずか足りなかったかのように、口元は不完全に開いており、その隙間から一本の葱が斜めに突き出ていた。葱の白い茎は街灯を受けて、わずかに水分を含んだようなぬめりを帯びて輝いていた。その白は、乾いた冬の空気のなかでは異様なほど濃く、周囲の黒いコートや灰色のマフラーのなかで、ひとりだけ別の温度をまとっていた。
彼女の服装は、よくある事務職のそれだった。膝下丈のタイトスカートは控えめに身体の線を拾い、黒いタイツが足首から太ももにかけて均質な陰影をつくっている。整えたはずの髪は後ろで束ねられているが、結び目のすぐ下からいくつかの毛束が零れ落ち、湿り気を帯びて首筋に貼りついていた。街灯に照らされると、その湿ったところだけが妙に妖しく光り、そこだけが生活の影を濃く孕んでいた。
横顔は、突出した美しさがあるわけではない。鼻筋も唇も控えめで、オフィスという均された空間のなかなら埋もれてしまいそうな凡庸さを持っている。それでも、目元にわずかに残った疲労の影や、まぶたの薄いくぼみの奥に、彼女の体温がゆっくり残っていた。私はその「わずか」に不意を打たれた。
信号が青に変わると、群れが波のように動き出す。女もそれにあわせて歩き出し、右手のレジ袋が揺れた。葱の白い茎がスカートのわきをかすめそうでかすめず、そのたびに袋の底が重たげに揺れる。露わになった白い線が暗い布の背景から浮かび上がり、歩幅に合わせて行儀悪く跳ねる様子は、妙な無防備さを帯びていた。彼女自身はそこに注意を払わない。むしろ袋の存在そのものを忘れているかのような、乱れのない足取りだった。
私はコーヒーを手にしながら、その滑らかな光景をただ目で追った。結ばれきらない袋の口元、乱れた髪、袋から突き出た葱の線。そのどれもが、彼女の生活の輪郭をわずかにこちら側へ押し出しているように思えた。彼女が地下鉄の階段を降りて姿を消すまで、私はその場から動かなかった。街灯に薄く煙る冬の帰路のなかで、あのレジ袋と葱の白さだけが、いつまでも目の奥に焼きついていた。
私は三十代で、都心の商社で管理職の肩書を持っている。管理といっても、その実態は人間関係の綻びを見つけ、利害を整え、もっとも摩擦の少ない方向へ物事を押し流すという、地味な作業の積み重ねにすぎない。正義や信念がどうであれ、優先されるのは数字と安定と秩序だ。私は早くからその仕組みを身体に馴染ませ、それに従って動いてきた。
職場では、誰がどの部下を嫌っていて、誰がどの上司に弱みを握られているのか、そういった情報のほうが、正しい理念よりもよほど役に立つ。人間は合理で動かない。理屈ではなく、習慣と畏怖と欲望で動く。その流れを読んで使わなければ、組織はまとまらない。私はそういう現実のほうを信じている。
そんな生活のなかで、彼女の袋と葱の白さは、思いがけず私の視界に残った。もっと正確に言えば、彼女の日常のほつれが、私の内のどこかを静かに撫でたのだろう。私は他人の綻びや弱さを観察することには慣れているが、彼女のそれは利害の計算と別の理由で、視線を引いた。
数日後、私はまた彼女を見かけた。駅のホームだった。夕方の雑多な空気のなかに、彼女は静かに立っていた。吊革を握る指先は細く、タイツ越しに覗く膝の丸みが、冬の光のなかでわずかに霞んで見える。右手にはまたレジ袋。今度は葱が二本かもしれなかった。口はさらに開いており、生活のどこかで「結びなおす」という動作が自然と省かれていることを、無言で示していた。
電車が揺れるたび、葱が膝を軽く叩く。白い茎は布地の黒に溶け込まず、むしろ浮き上がって見えた。袋のなかで他の食材の影が重たげに沈み、その均衡が少しずつ崩れていく。そうした小さな揺れのなかに、人間の暮らしの影はよく表れる。まぶたの影の奥に、職場の蛍光灯では照らしきれない温度が残っていた。装われたものではなく、一日の終わりまで消えきらずに残った呼気のようなものだ。電車を降りると、彼女は迷いのない歩みで雑踏に紛れ、やがて視界から消えた。しかし葱の白さだけは、空気に残る残像のように、しばらく私の眼の裏に滞留した。
それから、私は彼女を探すようになった。目的があるわけではない。意識していなくとも、視界のどこかで白い袋の揺れを探している自分がいた。気づけばその習慣は、帰路の一部として組み込まれていた。
会社近くのコンビニでも彼女を見た。冷蔵ケースの冷たい光が、彼女のコートの背中を淡く照らし、その輪郭を静かに浮かび上がらせている。右手のレジ袋にはやはり葱が突き出していた。豆腐らしき四角の影や惣菜がビニール越しにぼやけて見え、その手前で葱だけが鮮やかな線を保っていた。整えきれない生活の細部が、袋のなかに折り重なっている。生活というものは、芯とは別のところで、そのひとをよく表す。洗濯かごの丸まったシャツ、冷蔵庫に貼られるくたびれたメモ、床に落ちた髪の毛の一本。そうしたものは外の殻ではなく、内の繊維そのものを映す。彼女の葱も、その一本だった。
家へ戻ると、マンションの白い部屋と天井の均一さが、いつもよりも強く目につく。なにか不満があるわけではない。ただその静けさを前にすると、あの袋と葱の白さが心のどこかを押し広げる。均された白と、少し濁った白。どちらが生の匂いを持っているかは、考えるまでもなかった。
雨の日、私はついに彼女の生活圏の入口に触れることになった。冬の雨は輪郭を溶かすように降る。粒は細かく、数は多くないのに、空気を湿らせ、人の息遣いを浅くする。傘を差して歩いている私の肩にも、冷たい湿気がじっとりと染み込んでいた。
改札近くで、また彼女を見つけた。髪は濡れて首筋に貼りつき、コートの肩はしっとりと沈んでいる。彼女は傘を持っていなかった。あるいは、そういう用意の習慣が、彼女の日々から抜け落ちているのかもしれない。白いレジ袋は雨粒を拾い、半透明の膜をさらに濁らせていた。葱の白いところだけが、雨に磨かれていやらしいほど鮮やかに光っている。
電車が遅延して、人々は苛立ちを胸の底に溜めている。彼女は案内板を見上げて、濡れたコートの前を押さえ、少しだけ横に避けた。そのときレジ袋が脚に当たり、葱が細く揺れた。その揺れが、湿った空気のなかで生々しく感じられた。
私は傘を握る手に、すこしだけ余計な力をこめた。帰るべき家は別にある。それでも、濁った袋の白、濡れた葱の白、首筋に貼りついた髪の線が、私の内のどこかを静かに引いた。
彼女が改札を出て歩き出したとき、私は曳かれるようにその背中を追っていた。濡れた舗道には街灯の光が沈み、彼女の足跡が淡く反射している。葱の白さは歩くたび左右に揺れ、コートの裾と呼応する。袋から外へこぼれ出した一本の線が、夜気のなかで呼吸しているように見えた。
やがて彼女は、古いマンションの前で立ち止まった。三階建ての鉄骨造りで、階段は雨に濡れ、ところどころに黒い斑点が浮かんでいる。オートロックを開け、彼女は振り返らず階段を上がっていった。私はしばらくそこに立っていた。雨音、遠くの車のライト、濡れたアスファルトの匂い。すべてが静かに沈み、その沈黙の中央に、彼女の暮らしの入口だけがぽつりと浮かんでいるようだった。
気づくと、私はその入口に手をかけ、濡れた傘をそっと閉じていた。扉は指先をいったん弾くように軽く押し返し、やがて静かに開いた。階段の踊り場には小さな窓があり、滲んだ外灯の光が細長く貼りついている。金属の手すりは冷たく、足音が響くたび、階段の奥へ沈んでいった。
二階に差しかかったころ、上からかすかな衣擦れの音が落ちてきた。湿った布が肌を滑るときの、ごく小さな擦れだ。三階に着くと、短い廊下の突き当たりに小さなドアがあり、その隙間から黄色い光が漏れていた。
靴を脱いで一歩を踏み入れると、外気と違う温度が触れる。髪から落ちる水の匂いと、買ってきたばかりの野菜の青臭さが、混じり合っている。玄関は、生活と身体の境目にいつも溜まる匂いを、少し濃くしていた。
部屋は狭い。白いシーツをかけたベッドがひとつ、壁際に小さな棚、低いテーブルには茶色のランチョンマット。照明は暗く、電球がひとつだけ灯り、床のほうへ広がって影を長く伸ばしていた。影の長さで、室内のものの大きさと重さがわかるほどだ。
彼女は玄関から少し離れたところでコートを脱いでいた。肩から布が滑り落ちるとき、ブラウスの薄い生地が肌に貼りつき、その下の輪郭を淡く浮かび上がらせた。湿りを含んだ布越しに、肌がわずかに透けて見え、そこだけが夜のなかで熱を持っていた。
右手には、あのレジ袋。葱が半分ほど飛び出し、白い茎に雨粒が残っている。白濁した袋の膜は、部屋の灯りでいっそう厚みを増していて、外で見たときよりも中身の「重さ」を孕んでいるように見えた。彼女は袋をテーブルに置き、そのままキッチンに向かった。ここから先は完全に彼女の領分だった。
蛇口をひねる音がして、水が細く落ちる。彼女は葱を持ち、袖を肘までまくった。白い腕に細い血管が通い、灯りを受けてうっすらと浮かぶ。指先が葱をこするたび、葱が小さく鳴り、その音が部屋の静けさに吸い込まれていく。葱は食材にすぎないはずなのに、そのときだけ、人の身体のような存在感を帯びていた。鍋に湯が沸きはじめ、湯気が立ちあがる。その白い煙は彼女の頬を掠め、濡れた髪と混じり合って柔らかな影をつくった。湯気が消える一瞬のあいだにだけ、彼女の内の温度が浮かんでくる。
私は椅子に腰を下ろし、部屋の細部をひとつひとつ拾った。テーブルの端の小さなガラスの器には、飴色のヘアピンがいくつも入っている。そのうちの一本がわずかに歪み、結び目の緩さを思わせた。ベッドの足元には洗濯かごがあり、シャツやタオルに混じって、淡い色の布の端が覗いている。繊細なレースが、捩じれて、折れ曲がっていた。肌に密着していた時間の名残が、布の皺にそのまま残っているようだった。
そのレースを見たとき、私はようやく理解した。外から見える彼女と、この部屋の中の彼女は、まるで違う顔を持っている。地味で控えめな衣装の下に、別の色彩の層が隠れている。その色は誰かに見せるためのものではなく、自分の身体のためだけに選ばれたような、静かな強さを持っていた。
湯気の立つ鍋のまえで、彼女はしばらく動かなかった。湿った髪が頬にかかり、そこだけ影が濃くなる。タオルで髪を押さえ、ゆっくり外すと、髪が弧を描いて肩に落ちた。水気を含んだ毛先は、布よりも正直に、彼女の生活を語る。
視線をわずかに下げると、ブラウスの胸元がかすかに透け、下に纏った布の輪郭が淡く浮かんだ。白でも青でもない、夜の色を含んだような布。その縁は細く、静かな曲線を描いていた。彼女の日中の印象から考えれば、あまりに対照的な色だった。彼女はそれに気づいているのかどうか、判らない。襟元を整える仕草は途中で止まり、布は完全には閉じられないまま残った。整えきれないその一点から、彼女の「本来の色」がじわりと外へ滲み出していた。
彼女が包丁を置き、鍋から離れたとき、ブラウスの裾がふわりと揺れた。湿った生地が身体に添って、隠しているはずの曲線をなぞる。ベッドの端にタオルを置くと、そのすぐ横で、さきほど見えたランジェリーがまた少し覗く。彼女はそれを直そうとしない。疲れが先にあり、整えることが後回しになっている身体の動きだった。
私は椅子に座ったまま、息を浅くして彼女の動作を見ていた。濡れた髪をタオルで押さえると、首筋を流れた水滴がブラウスの襟元を濡らし、そこから布を細い筋となって下りていく。その線が、地上で揺れていた葱の白い茎の線と重なり、一本の抽象的な線として私の内に残る。
ベッドに腰を下ろした彼女は、足元のタイツに手を伸ばした。足首のあたりでたるんだ布を伸ばすために、親指をタイツの内へ差し入れ、そっと引く。布が肌に吸いつく小さな音がして、その音がこの部屋の空気にしみ込んだ。薄い抵抗に押し返されるように肌が盛りあがり、その一瞬の形がタイツ越しにくっきりと浮き出る。
視線を逸らす理由を探しながら、結局は逸らせないまま、私はその動きを見ていた。声を発しなくとも、彼女の身体は「ここに生活がある」と、充分すぎるほど語っていた。濡れたブラウスが乾くにつれ、布地は少しずつ張りを取り戻し、胸元に吸いつく。肩口の縫い目が動きに合わせてわずかに引かれ、そのたびに薄い影が脇へ移る。彼女が軽く腕を上げたとき、脇のボタンのあたりに布の張りが生まれ、その下に潜む熱を、布は隠しきれずにいた。
やがて彼女は立ち上がり、キッチンへ戻ろうとした。腰骨のあたりでブラウスの裾がふとめくれ、深い色のレースが一度だけ息をするように姿を見せた。その瞬間、部屋の空気がわずかに変わる。灯りの角度も、椅子の硬さも、位置をずらした。
鍋からふたたび湯気が立ち上がる。白い立ち上がりが、レジ袋の濁りと重なって見える。どちらも、中身を包みながら、どこかでそれを洩らしている。私は椅子に沈み込んだまま、その白い膜の向こう側にいる女の背中を見ていた。この部屋に足を踏み入れてからの私は、彼女の暮らしのなかに挿し込まれつつある、とゆっくりと理解する。あれこれ理由を並べなくてもよい。ただ、ここにある温かさと匂いと湿りが、それを証明していた。
湯気はやがて薄れ、灯りの下に彼女の背だけが残った。布越しの影と、乾ききらない湿りの名残が、私をさらに静かな深いところへと沈めていった。